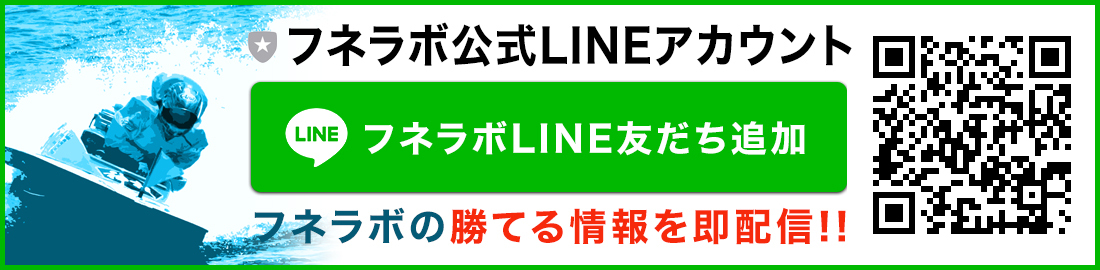競艇用語の「キャビる」って一体何!?どういう時に使うの?

競艇用語って、時折なにこれ?っていうようなワードもあったりしますよね。
本日はその中から「キャビる」について説明させて頂きます!
実は競艇(ボートレース)において結構大事な言葉だったりもするので、しっかりと覚えちゃいましょう!
目次
そもそも「キャビる」とは?

皆様は「キャビる」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
語感的には「タピる」になんだか似ていますね~。
正式には「キャビテーション」を起こす事を指します!
ではそんな「キャビテーション」というのは一体何なのでしょうか~?
今回は、キャビテーションについて説明させて頂きますね♪
「キャビテーション」とは
「キャビテーション」は水中に発生した気泡により、プロペラが空転状態になる事により推進力がなくなって減速してしまう現象です。
まずプロペラの仕組みとして、高速回転を行う事によりプロペラ前の水を吸い込み後ろに噴出する事によって進むように出来ています。
キャビテーションは、その動きによって発生した気圧差によって押し出された水が沸騰する事によって泡が発生する現象です。
これは、シャコのパンチによって発生すると言われているキャビテーションとも同じ原理です!
…冷静に考えて、シャコのあの小ささから繰り出されるパンチが科学の結晶であるモーターと同じ現象を引き起こすって、スゴくないですか?
失礼、話が逸れてしまいました!
ともかく、競艇においてよく言われている「キャビる」というのは、キャビテーションによって発生した泡をプロペラが吸ってしまう事により(プロペラが)空転してしまう事を指しています。
そしてその現象は、仕組み的にも主に後続の舟が前を走る舟の走行で発生する「引き波」を吸い込んでしまう事で発生する事が多いとも言われています。
「引き波」というのは舟の走行によって発生する白い波の事で、先程お話したように「キャビテーション」現象によって発生した泡がたっぷり含まれています。
もちろん先頭を走る舟がキャビらないという事ではありませんが、可能性的には後続の舟が陥りやすいというのは納得出来る話ですね。
実は昔からあった?いつ頃生まれたワードなのかを深掘り

では、そんなキャビテーションを略した「キャビる」ですが、いつ頃に生まれたのでしょうか?
語源が分かると、いつから言われているのかも凄く気になりますよね。
計測としてまずはTwitterでの最古のつぶやきで調べてみたいと思います。
ワード指定して検索を遡って行きますよ~☆
さて、まずは「キャビる」というワードを指定して検索した所、最初の投稿は2009年でした。
この地点でおよそ13年前…という事は、かなり長く使われてきたワードだという事が分かりますね。
次にワードの振れ幅を考えてみます。
「キャビる」という言葉をある程度変化させるとなると、「キャビった」「キャビってる」「キャビっちゃった」が考えられます。
なので全てに共通する「キャビっ」をワードに指定して検索を掛けてみます。
するとこちらも「2009年」が初出でした。
Twitterは2008年に日本版がスタートしているので、もしかしたら競艇に関する事を呟くユーザーが当時Twitterには少なかった可能性もありますね。
次はGoogleにおいて検索日時の範囲を絞って検索してみた所、2002年に更新されたサイトが出てきました。
うーん…思ったよりも深い歴史ですね、もしかしたらかなり昔から普通に競艇場では良く使われていた言葉なのでしょうか?
今となっては知る由もない、言葉のロマンですね~。
レース中にキャビるとどうなってしまうのか
それではキャビテーションを起こしてしまった際の影響についても触れていきたいと思います♪
キャビってしまうとプロペラが空転を起こして速度が落ちてしまうというのは先程もお伝えした通りですね。
では実際、どれぐらいの速度低下を起こしてしまうのでしょうか?
超高速で走行するボートにとって、キャビテーションは急ブレーキしたようなもので、キャビってしまった舟は一気に推進力を失ってしまいます。
ましてや時速約80kmともされる世界で推進力を失ってしまうのは車で言う所のハイドロ・プレーニング現象に近いかもしれません。
そのような状況から立て直す、というのは現実的に考えてもかなり厳しいと言わざるを得ないでしょう…。
大体は他の舟に抜かれて順位を下げてしまう事が往々だと思います。
また、更に恐ろしいのが他舟との接触です。
舟が密集するターンマーク付近で急激に速度を失ってしまった舟があると、周囲の舟も避けきれずにぶつかってしまう…という事なんかも。
予想には活かせるか
では、先んじてキャビテーションを予想する事は出来るのでしょうか?
答えから言ってしまうと、事前予想は難しいと言えるでしょう…。
キャビテーションはその性質上、どれほどモーター周りが正常であっても発生する可能性は常に存在しています。
ですので、我々が事前予想によってキャビテーションを起こす舟を見分ける、というのは殆ど無理といっても差し支えないです。
未来予知が出来るのならば、別ですが…。
その他の謎言語についても、少しだけご紹介!
さて、あらかた「キャビる」については説明をさせて頂きましたが…。
競艇には、他にもいくつか難解なワードが登場いたします。
「キャビる」のついで、ではありますが、せっかくですので軽く紹介させて頂きますね♪
賭け事においてよく聞く「トリガミ」
まずは、レースを予想する際に良く聞く「トリガミ」という言葉から説明させて頂きます!
言葉のブレとしては「ガミる」や「ガミった」などと略されている場面も良く見ます。
使う場面としては購入した舟券が的中したが、収支的にはマイナスな時に使われていて、競艇以外でも、競馬や他公営ギャンブルでも使われていますねっ☆
語源に関しては「粋が身を食う」という故事が元だとする説が最有力とされています。
「粋が身を食う」の意味合いとしては、遊びに長けた人がそれにのめり込み過ぎて体や生活がボロボロになることです。
…どちらにせよ、勘弁願いたいですね~。
IN選手の重要テクニック「先マイ」
次は「先マイ(サキマイ)」という言葉についても説明させて頂きます♪
こちらの語源としては「先に回る」という意味を持っています。
先マイは、他艇よりも先にターンマークを決めるテクニックになっています。
先んじて回る事でどんな事が起きるかと言うと、後続の舟を引き波の中に引き入れる事になるんです。
引き波の怖さは「キャビる」の項目でも説明したように、先マイは他舟の速度低下も狙えるテクニックにもなっています。
先マイと対をなす「ツケマイ」
次も似たようなワードですが、「ツケマイ」についてもご紹介しちゃいます!
先からのツケ…となると、もうある程度想像も出来るかもしれませんね。
ツケマイは、2コースよりも外側の舟が内側の舟にピッタリとくっついて抑え、引き波の中に抑え込むテクニックです。
先マイとは相対関係のような物と言っても良いと思います。
ちなみに先マイ・ツケマイ両方に共通する「マイ」ですが、こちらは競艇において「回る」という意味になっています。
キャビるのそっくりさん?「ブルが入る」
最後に「キャビる」の意味と似ている物として上げられる事もある、「ブルが入る」についてをご紹介して終わりにしたいと思います!
「ブルが入る」というのは、エンジンが正常に働かず、プロペラが異常な動作になる現象です。
発生する原因としては、キャブレーターが水分を含んだ空気をエンジンに送り出してしまう事により、燃焼を正常に行えずに加速がおかしくなってしまう事が挙げられます。
加速が出来なくなるという点では同じですが、別物ではあるので分けて覚えるようにしましょう!
まとめ!キャビるは昔から使われている重要ワード!
今回は「キャビる」を始めとした競艇のワードを幾つか紹介させて頂きました♪
競艇には初見じゃ絶対分からなくない?っていう用語がたくさんありますので、今回紹介した言葉以外にも気になるワードがありましたら、是非ご自身でも調べてみてくださいね。
それでは、読アでゅ~☆
(※読んで頂きありがとうございました、またお会いしましょう!)

- ☆よく寝る子ちゃん☆
- 競艇界に降臨したバーチャルライターなのです~♪ 前職が競艇予想サイトの中の人ってことは誰にも言わないで欲しいのです〜( *ˊᵕˋ) 予想サイトの会社はほぼ把握してるし、私が見ればすべて丸裸なのです〜☆
記載の内容はあくまでもレポーター独自の見解であり、内容の正確性・再現性を保証するものではありません。紹介しているサイトのご登録・ご利用は自己判断でお願いします。